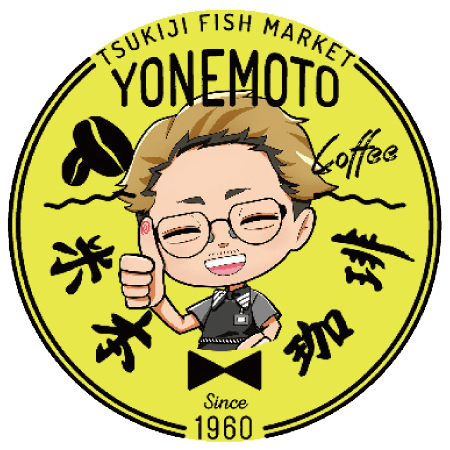米本百々子(H21.3.24逝去81歳)
(昭和3年生まれ)ヨネモト- 私って商売もできるんだなって
思ったのがきっかけ
晴海通りに面したコーヒーショップ「ヨネモト」の店内は、築地で働く人から買い物客まで、いつも老若男女でにぎわっている。「ヨネモトのコーヒー飲まないと始まらない、終わらない」というおいしいコーヒーに加えて、マスターの米本謙一さん一家の明るいアットホームな雰囲気も大きな魅力である。
昼すぎからカウンターに立つのは、謙一さんの母、米本百々子さんである。
78歳とは思えないほど、若々しく、モダンな女性。とても気さくな人柄なので、カウンターに腰掛ける常連のお客さんとの会話もはずむ。
ヨネモトは昭和35年、専業主婦だった百々子さんが嫁ぎ先の果物屋の隅でパンの販売をしたのが始まりである。
そのきっかけは、なんと少女時代にまでさかのぼるのかもしれない。話をうかがうと大いにうなずける。人生とは、偶然の点の積み重ねではなく、一本の線でつながっているのではないかと思われるほど、百々子さんが駆け足で語った半生は、いつか読んだ何かの小説を思い起こさせるようで懐かしい気がした。
百々子さんの実家は大森で鮮魚店を営んでいた。女学校を卒業していすゞ自動車で秘書の仕事についたが、ここで後に夫となる米本清之助さんと出会うのである。その話は後述するとして、戦時中の思い出は、昭和19年に小学6年だった弟
たちの学童疎開の寮母として富山県氷見市の寺で生活したことである。
「親は死んでもいいからおまえたちは生き延びろ」とは当時の親たちの切実な気持ちだったのだ。近所の人たちに「百々子さんが子どもたちといっしょに行ってくれるなら安心」と言われ、百々子さんは「わたしは姉さんなのだ。この子たちの面倒を見よう」と心に決め、子どもたちといっしょに氷見市へ向かった。寺小屋では、小学6年の学童28人の受け持ちになり、勉強を教えたり、まきを運んだり、洗濯したりという忙しい生活だった。翌年3月に6年生は卒業というので東京へ帰ったが、百々子さんは5年生といっしょに氷見に残った。そして4月、京浜地区が大空襲により、大森の焼け野原と化したのである。このとき実家も焼けてしまったのだが、富山にいた百々子さんには家族の無事を知るすべもなかった。
「わたしは富山にいて、一時、家族とは音信不通になってしまったのね。日本はおしまいかな、天涯孤独かなと思いました。2カ月後、東京で怖い目にあった3年から6年までの子どもたちがこちらに来ました。3年生なんて、あまりにも小さくて涙が出たわよ。この子たちを死なせないぞという思いで、1年くらい一緒に生活していました」
終戦後、富山から大森へ戻ってまもなく、蒲田の駅でいすゞの上司とばったり会った。「また、うちにおいでよ」と声をかけられ、再びいすゞへ。そこへシベリア抑留となっていた米本さんが無事に帰還し、いすゞで再会することになるのである。これが縁で二人は結婚することになるのだが、その矢先に父親が脳 溢血で急死。
主を失った魚屋を一時は閉めようと思ったが、百々子さんは弟といっしょに切り盛りして営業を続けた。
「自転車で仕入れに行って、弟は大森の駅の向こうまで魚を売って歩いたのです。父が死んで同情してくれたのね。みなさんが来てくれたおかげで店を続けることができたのよ。暮れに正月用品の注文をとって、弟にお得意さんを回らせまし
た。ここで、商売は面白いと思ったのでしょうね。夫も実家にいていいということになり、4年ほど実家にいて手伝ったのよ」
話は前後するが、現在地のヨネモトが誕生するきかっけは戦前に遡る。百々子さんの夫の清之助さんの父は京橋の大根河岸で運送店を開いていたが、昭和10年、市場の築地移転に伴い、運送店も築地へ。そして自宅は湊町へ越したのだが、戦時中に区画整理があったため、現在地の周辺に土地を探していたところ、大家の昆布屋さんが「借家が空いていて物騒だから、留守番がてら入ってくれ」と言われて移り住んだのが現在地。1階に四畳半と台所、2階には4部屋。百々子 さんが嫁いだころには、運送会社を定年退職した義父は果物を売っていたという。
小学校に通うようになった長男の謙一さんが「パンを食べたい」と言った。しかし、近所にパン屋さんはなかった。ふと思いついたのが、果物を売っている店先のほんの一部分で「パンを売ってみよう」だった。利益は考えないで、主婦業をしながら販売できるというので、パン屋さんに注文すると配達してくれた。百々子さんは店頭でパンを売り始めた。あんぱん、ジャムパン、コロネ、クリームパン、メロンパン。これが見事に当たった。
「パンが面白いように売れて、楽しくてしょうがなかったわ。ドックパンにキャベツと揚げたカツをはさんだカツサンドをつくって店に出したところこれもすぐに売れたのね。揚げパンアンパンだけで100個も売れましたよ。午前中に売り切れたわね。
まだ、お弁当屋さんがなかった時代だったのでパンは重宝したのよ。二人目の子どもをおんぶして接客していました」
小学生の謙一さんが登校前の早い時間に、ジャムやバターを塗ったコッペパンの入った大きな袋を二つぶらさげて、近所のお得意さんに配達したという微笑ましいエピソードもある。
やがて、大学卒業をひかえた謙一さんが「おふくろが一人でたいへんだから店を手伝うよ」と言い出した。百々子さんは驚き、「社会に出なさい」と勧めたが、息子の意志は固かった。喫茶店も始めた。
「あとは息子にまかせることにしたの。主人もいすゞを辞めて店を手伝うようになったし、息子が結婚して夫婦で店に出て、家族で盛り上げていったのよね」
現在の「コーヒーのヨネモト」のスタイルにしたのは22年前である。そのころ400円くらいのコーヒーを200円という安価で提供するという大冒険。いまでこそ、安いコーヒーショップは氾濫しているが、それのはしりだった。お客さんが「200円にしたらやっていけるのか」と心配してくれたが、安くて おいしいコーヒーに人気集中した。
「私は父に死なれたあと、魚屋を自分でやってみたら、あら、私って商売もできるんだなっていう気になったのね。だから、結婚しても自分は何かできるのではないかと思ったんですよ。果物屋の店先のほんの一角でパンを売ってみて、あんなに売れるとは思ってもみなかったわよ。いい経験でした」
淡々と語る百々子さんは、「いまね、うちの孫娘が手伝いに来ているのよ」 と顔をほころばせた。

(平成18年 龍田恵子著)